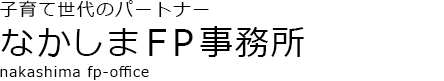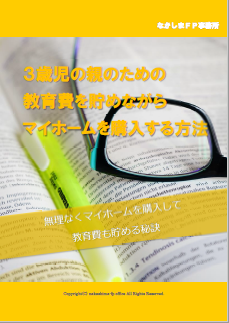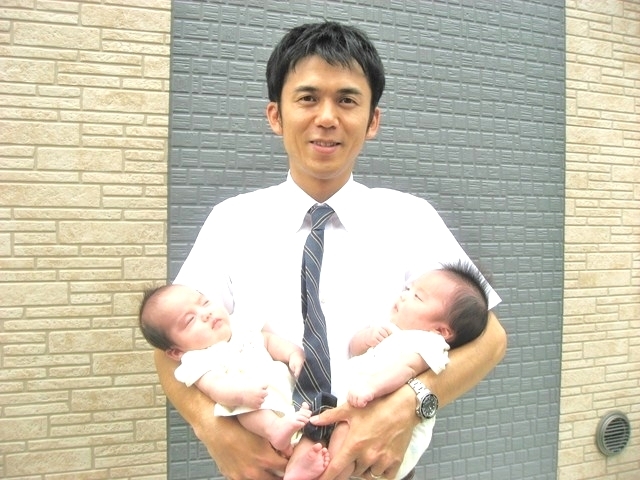「ライフプラン」 、「生命保険見直し」 、「住宅ローン相談」 など、ファイナンシャルプランナー(FP)が子育て世代の家計見直しをサポートします!
生命保険見直し術
加入目的の確認
保険に加入するときや、見直すときは、そもそもなぜ保険が必要なのかという、加入目的に
戻って考えてみましょう。
一般的には、自分が万が一のとき、遺された家族が、経済的に困らないようにするためと、
病気やケガをしたときの医療費などに備えるため、というのが一番の目的のはずです。
さらに、子どもの教育費や老後資金を準備するための、貯蓄を兼ねて利用する人もいるで
しょう。このようにニーズに合わせて、生命保険はには大きく分けると
「死亡時に備える保険」
「病気やケガに備える保険」
「貯蓄を兼ねて備える保険」
の3つのタイプの保険があり、それぞれの目的に合わせてさまざまな種類が用意されてい
ます。
3つのタイプのうち、肝心なのは死亡保障と医療保障なので、これを適切な額で優先的に
確保しましょう。貯蓄を兼ねて備える保険は、他の金融商品にはないメリットと、保険料のバ
ランスを考えて検討したいものですね。
生命保険は最低必要な保障をカバーするものと割り切って、余裕資金ができたら、貯蓄や
ローン返済などに回してもいいと思います。
逆に、貯蓄もできないほどたくさんの保険料を払っていたり、保険料を払えないほど家計が
苦しいという場合は、払える範囲の保険料で必要な保障をできるだけ確保するということに
なります。
あらゆるリスクを想定して、万一のときに働かなくても一生暮らしていけるくらいの金額を保
険だけで準備しようとすると、保険料も高額になり、きりがありません。
万が一の場合に備えるあまり、保険に加入しすぎて家族との生活を楽しめなくなるのは本
末転倒ですよね。
保障内容の確認
契約時の保障設計書、保険証券などを用意して、主契約、特約の内容を一つ一つ確認して
いきます。誰にいつまでどのくらいの保証がついていて、何を保障の目的としているかチェッ
クします。
死亡(高度障害)した場合の保障はいくらか。死亡保険金が分割で支払われるものはあるか。保障額は一定か、減少していくのか。交通事故などの不慮の事故で死亡(高度障害)した
場合はいくら上乗せされるか。また、病気やけがで入院(手術)した場合の保障はどうなっ
ているか。それぞれの保険はいくらいつまで払いこむのか、などです。
保険をかける場合は、まず、シンプルに死亡と入院保障とに分けて、必要最低限の形で設
計してみることです。場合によっては、これだけでいいかもしれません。これをベースに必要
に応じて、死亡、入院を補完する各種特約をつけていきます。
また、世帯主の死亡などによる「死亡リスク」と病気やケガの治療費などの「生存リスク」は
別物なので、特約で付加するのではなく、それぞれ単品で加入する方法もあります。
また、貯蓄性重視の保険と保障重視の保険のどちらを選択するかも、加入目的によって違
ってきます。
分散して掛ける場合は複数商品に加入することにもなりますので、しっかり管理していき、そ
の時々の実情に合わせて定期的に見直すことが大切です。また、家族全員でいくつかの保
険に加入しているケースが多いので、一覧表を作ることをお勧めします。
自分で準備する医療保障はどのくらい?
入院にかかる自己負担は?
①差額ベット代(公的医療保険で決められた室料との差額、大部屋は自己負担なし)
差額ベット代の相場は、1日5,000円以下のところが6~7割です。
②健康保険対象外の特殊な治療費(先進医療の技術料など)
先進医療にかかる技術料は、患者の負担で200万円を超える例もあります。
③入院時の食事代(1食260円) ※一般被保険者
④その他の雑費(家族のお見舞い時の交通費、日用品、快気祝いなど)
高額療養費制度で治療費の自己負担は限定的です。
70歳以下の方の自己負担限度額は以下の通りです。
・月収53万円未満の人は、月額80,100円+(医療費−267,000円)の1%
・月収53万円以上の人は、月額150,000円+(医療費−500,000円)の1%
・住民税非課税世帯は、月額35,400円。
これを超えた部分は払い戻されます。
入院給付金の給付日額の目安は?
予備費としての貯蓄とあわせてバランスよく備えましょう。
治療費は高額療養費制度で一ヶ月80,100円でなら、1日当たり2,670円。
差額ベット代が5,000円前後として、
・会社員 給付日額 7,000円~10,000円
・自営業者 給付日額 10,000円~15,000円(国民健康保険に傷病手当金が無いため)
・専業主婦 給付日額 5,000円~7,000円(子どもが小さいときは少し多めに)
くらいが目安です。所得が高い人は、自己負担が高い分少し多めでいいと思います。
それから何歳まで医療保障を必要とするか、1回の入院で何日分まで入院給付金を
確保するか、先進医療や女性疾病医療などの保障を付けるかを考えていきます。
生命保険の入院給付金は、一定期間を経過しないと支払われないものもありますが、
最近では短期入院をカバーできるものが主流です。
お電話・メールでのご相談は無料です。
わからない事や不安なことはお気軽にご相談ください。
tel:045-512-6093(受付時間 月~土曜 9:00~18:00)
どこをどう見直せばいいの?
見直し保険金額
必要保障額と既に加入している死亡保険金合計額の差額が見直し保険金額です。
必要保障額4,000万円、既加入保険金額合計5,000万円なら1,000万円保険
金額が多いことになります。
しかし、保険料の支払い余力があり、かつそのくらい保障がないと不安という場合
にはそのままでもよいと思います。
一般的に、必要保障額は末子が誕生したときに最も大きくなり、その後は、子どもが
大きくなるにしたがって年々減っていきます。定期的に見直す中で、保険金額を下げ
ていくと効果的です。
住宅の購入も必要補償額を減少させせる要因になります。団体信用生命保険付の
住宅ローンを利用すれば、万一の場合にローン残債は保険金で完済され、遺族生活
費のうち住居費が減少するためです。
見直しの主な方法
1.現在保険金額が多い場合
定期保険特約・特定疾病医療特約の一部解約・減額・払済保険・解約
などの方法があります。
2.保険金額が足りない場合
特約の中途付加・中途増額・新規契約などの方法があります。
医療特約を中途付加・増額すると、責任準備金の差額を支払わなければ
ならないので、単体の医療保険に加入した方が安いケースもあります。
3.保険料の負担を軽くしたい場合
減額・払済保険・延長保険・解約・払込期間の変更などの方法があります。
予定利率※1の高い貯蓄性の保険は残し、定期保険は他の保険会社の
安いものに買える方法もあります。
4.税金の負担を軽くしたい場合
契約者(保険料負担者)以外の人が満期保険金を受け取ると贈与税
がかかります。税率が高くなるので受取人を契約者(保険料負担者)
に変えましょう。(所得税)※2
5.保険会社、商品を比較検討する。
複数の保険会社から見積もりを取ったり、パンフレットを取り寄せましょう。
同じ保障額で保険料を比べ、じっくり検討して加入する保険を選ぶことが大切です。
※1.予定利率とは、生命保険会社が将来保険金を支払うために積み立てる
際の予定の利率です。予定利率は平成元年頃をピークにだんだん下が
ってきています。
※2.満期保険金を保険料負担者が受け取った場合、所得税がかかります。
(一時金で貰う場合は一時所得、年金で貰う場合は雑所得になります。)
ここまでで、あなたの必要保障額や、それにどこまで保険で備えればいいかは
各家庭によってさまざまであるということを理解していただけたと思います。
それは、あなたの家計の事情もさることながら、考え方と気持ちによるところが
大きいからです。
生命保険の商品や内容等はあなた自身がすべて決めることが出来るもの
なのです。
生命保険8つのチェックポイント
1.保険証券記号番号
家にある保険の書類をすべてこの保険証券記号番号ごとにわけてファイルしてください。
保険証券・お見積書(設計書)・ご契約のしおり・約款・保険内容のお知らせ・決算のお知
らせ・保険料控除証明書などです。
同じ書類があったら、最新のものだけ残して前年度の書類は破棄してください。契約当時
に保険会社の担当者からもらったメモや資料などは捨てないで保管しておいてください。
2.保険の種類
主契約の適用約款欄に書いてあるものを記録。愛称○○プランのようなものではなく、正
式名△△配当付き××保険と書いてあるほうです。
3.契約日
保険の予定利率がわかります。被保険者の契約年齢欄では、加入した時の年齢がわか
ります。
4.契約形態
受取人は受け取ってほしい人の名前になっていますか?契約時の印鑑も保管されてい
ますか?保険契約者(通常は保険料を払っている人)・被保険者(保険の対象になって
いる人)・死亡保険金受取人または満期保険金受取人がだれかによって、受け取り時の
税金が変わります。
5.死亡保険金額
主契約と特約それぞれ保険金の病気死亡時の金額を合計してください。三大疾病(特定
疾病)保険特約も加えてください。その保険金が、将来どう変わるかもチェックしてみまし
ょう。逓減定期保険のように毎年保険金額が減額されるものもあります。
収入保障特約の年金やこども保険の育英年金は、「生活保障特約または、育英年金」欄
に書いてください。
6.保険期間
保障がいつまで続くかを確認してください。定期保険特約付終身保険の場合、終身保険
の特約の保険期間が、保険料払込期間と同じ場合は全期型、短い場合は更新型です。
更新時の保険料は再計算されますが、当初より必要補償額が減少した分、保険金額は
減額して更新してもよいのです。また、医療特約の保険期間は80歳までになっている場
合がほとんどです。
7.保険料
払込期間で、いつまで払うかを確認してください。ステップ払いでは、ステップ期間終了後
に保険料が上がります。終身保険に医療特約が付いている場合は払込満了時に残りの
期間の保険料を一括で支払いますが、更新型の場合は支払う金額が更新の都度大きく
なるので注意してください。
8.入院特約
病気入院・ケガ入院・生活習慣病入院・がん入院のそれぞれの給付日額を確認してくださ
い。家族型は、夫が万一の場合、妻子の保障がなくなるタイプが多いのですが、その際の
準備ができているか確認しましょう。
お電話・メールでのご相談は無料です。
わからない事や不安なことはお気軽にご相談ください。
tel:045-512-6093(受付時間 月~土曜 9:00~18:00)
お問い合わせはこちら
無料小冊子プレゼント
事務所概要
なかしまFP事務所
代表者:中嶋 健三
プロフィールはこちら
ご相談場所
〒221-0835 神奈川県横浜市
神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル7F KFPオフィス
本社事務所
〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町291-13
ご連絡先はこちら
事務所概要はこちら
交通・アクセスはこちら