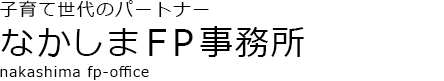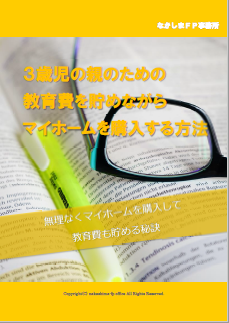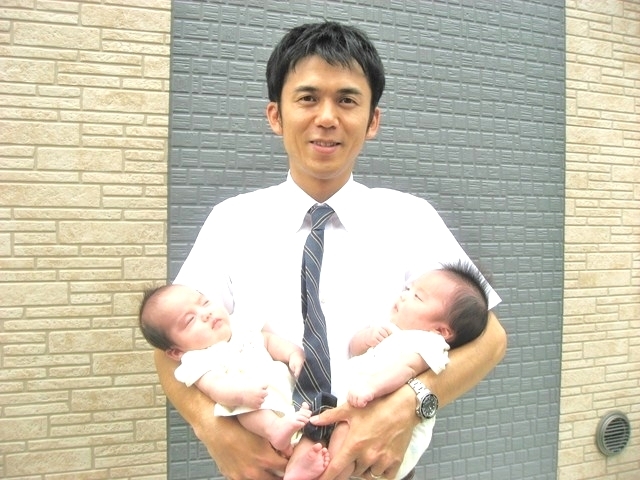「ライフプラン」 、「生命保険見直し」 、「住宅ローン相談」 など、ファイナンシャルプランナー(FP)が子育て世代の家計見直しをサポートします!
生命保険見直し術

万が一のとき、遺された家族が経済的に困らないように備えるのが生命保険。問題はどのくらいの補償額があればいいかです。
通常、夫に万が一のことがあれば、遺族年金が遺された家族に支給されます。妻の収入が見込めるなら、その収入や遺族年金などを考慮して、夫は不足する分を民間の保険でカバーするという考え方が基本です。
必要補償額の計算方法
必要補償額の計算は、子どもが独立するまで最低限は保証してあげたいという場合、次のような式で計算できます。
月の生活費×0.7×12ヶ月×(22歳-末子の年齢)=遺族必要補償額
これは、夫が万が一の場合、一ヶ月の生活費は7割くらいになると考え、それが12ヶ月で1年。さらに子どもが独立するまで(22歳)から現在の末子の年齢を引いた額が、現在の遺族の必要補償額になるという考え方です。
つまり、子どもの年齢が上がるとともに、子どもが独立するまでの期間が短くなるので、必要補償額はだんだん少なくなっていくということです。
万が一のときは遺族年金がある
夫に万が一のことがあった場合は遺族年金が遺された家族に支給されます。
会社員の夫が万一の場合、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の合計で
| 子ども一人の場合 | 12万~14万円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 子ども二人の場合 | 14万~16万円/月 |
が子どもが18歳になった年の年度末(3月)まで支給されます。
なので、保険で備える分は、上で計算した遺族の必要額から。この遺族年金の分を差し引いて考えます。
持ち家と賃貸の場合で変わってくる
持ち家で住宅ローンを組んでいる場合、「団体信用生命保険」というものに入っています。
これは、住宅ローンを組んでいる人に万が一のことがあった場合は、住宅ローンが無くなって家は遺された家族に残るという、いわゆる保険です。
つまり、持ち家で住宅ローンを支払い中の場合に万が一のことがあったら、残りの住宅ローンは無くなってしまうということです。
例えば、会社員の夫で、子ども一人(3歳)、住宅ローン残り3000万円という場合、
夫に万が一のことがあったら、遺された家族の家計はどうなるのでしょうか?
- 住宅ローン(3000万円)は団信で0円になり、マイホームは家族に残る。
- 遺族年金が子どもが18歳まで約14万円/月 支給される。
これから、さらに足りない部分があれば、その部分だけ保険で準備すればいいわけですね。
生命保険相談はこちら
無料ガイドブック(PDF)プレゼント!
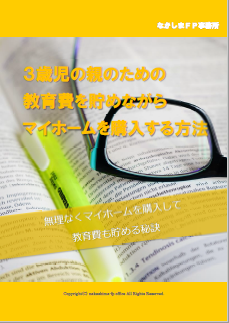
PDF版(15ページ)
3歳児の親のための教育費を貯めながらマイホームを購入する方法
このガイドブックを読むことで
・無理なく買えるマイホーム金額の算出方法とは?
・変動金利VS固定金利どちらがお得?
・劇的に教育費が貯まる3つの秘訣
など、マイホーム購入のポイント、効率的な教育資金の貯め方、貯蓄が増える家計の管理方法など、具体的な方法がわかります。
これまで800世帯以上の家計を見直した中で、これだけは知っておいてほしいというポイントをまとめました。
あなたのマイホーム、教育資金の準備にお役立てください。
ガイドブック無料ダウンロードはこちら
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
なかしまFP事務所トップページ
お問い合わせはこちら
無料小冊子プレゼント
事務所概要
なかしまFP事務所
代表者:中嶋 健三
プロフィールはこちら
ご相談場所
〒221-0835 神奈川県横浜市
神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル7F KFPオフィス
本社事務所
〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町291-13
ご連絡先はこちら
事務所概要はこちら
交通・アクセスはこちら