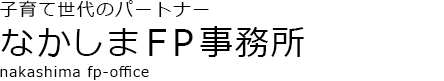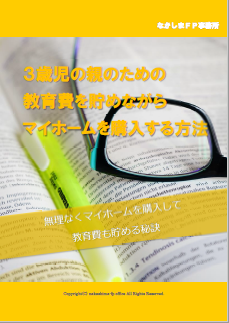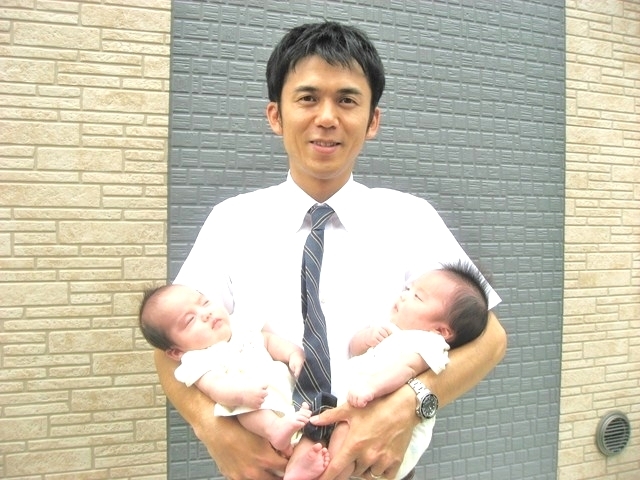「ライフプラン」 、「生命保険見直し」 、「住宅ローン相談」 など、ファイナンシャルプランナー(FP)が子育て世代の家計見直しをサポートします!
Q.保険金にかかる税金
保険金には税金のかかるものとかからないものがある!
もしもの時の備えとして頼りになるのが生命保険です、しかし、保険金の種類や契約の仕方によって税金がかかることもあるってご存知ですか?
税金がかる対象となるのは、死亡保険金や満期時に受け取る保険金、個人年金の年金、こども保険の祝い金、解約返戻金など。
保険金にかかる税金は、保険の種類や契約形態によって違ってきます。
契約形態とは、契約者、被保険者、受取人など、その保険の「名義」が誰になってるかということで、税額を大きく左右する要因になります。
税金のかかるもの
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 個人年金保険の年金
- 祝い金・生存給付金
- 解約返戻金など
税金のかからないもの
- 高度障害給付金
- 特定疾病保険金
- リビングニーズ特約保険金
- 入院・通院・手術給付金
- 介護年金・介護一時金 など
名義や受取人の組み合わせで、税金はこんなにも違う
死亡保険金
受取人が配偶者なら相続税がかかります。ただし、生命保険の非課税枠分
(500万円×法定相続人数)に加え相続税の基礎控除分
(3000万円+600万円×法定相続人数)を保険金から差し引くことができます。
なお、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は、税率が高い贈与税がかかってしまいます。可能なら名義変更の検討を。
満期保険金
契約者と受取人が同じなら一時所得扱いになり所得税(+住民税)がかかります。
払込保険料など差し引ける部分が多いので、受取額によっては税金がかからないか、それほど高くないケースが多いでしょう。
契約者と受取人が違うと贈与となり、受取人が贈与税を支払うことに。専業主婦や子供を受取人にするのは避けたほうが無難です。
個人年金保険
このケースは契約形態にかかわらず雑所得の対象になり、所得税(+住民税)がかかります。
ただし、契約者と受取人が異なると、契約者から受取人への贈与となり、年金の権利評価額(確定年金は残存期間に応じて年金総額の2~7割)に対して贈与税がかかってしまいます。
つまり、所得税と贈与税をダブルで支払うことに。
契約者が収入のない妻で、夫が保険料を払っているときも贈与とみなされてしまいます。
その場合は、保険料自体を夫から贈与してもらいましょう、年間110万円以内の贈与なら贈与税はかかりません、妻の口座に保険料を振り込み、保険料は口座引き落としにするのがベストです。
保険の種類によってかかる税金はさまざま
死亡保険金にかかる税金
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 〇 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 一時所得 | △ |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | ×(注意) |
満期保険金にかかる税金
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | |
| 夫 | 妻または夫 | 夫 | 一時所得 | △ |
| 夫 | 妻または夫 | 妻 | 贈与税 | ×(注意) |
個人年金にかかる税金
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
| 夫 | 夫 | 夫 | 雑所得 | △ |
| 夫 | 妻 | 妻 | 贈与+雑所得 | ×(注意) |
可能なら契約の見直しも検討しよう。
税金の種類によって税額はかなり違ってきます。可能なら契約の見直しも検討しましょう。
一番税率が高いのは「贈与税」。
たとえば、本人と妻、子供2人の家族で、死亡保険金が1000万円をすると
相続税の場合
1000万円ー※1500万円=▲500万円
※生命保険の非課税分 500万円×法定相続人
税金はかからない(生命保険の非課税枠に収まるので)
贈与税の場合
※1保険金 ※2基礎控除枠 贈与税の税率 控除枠
(1000万円 - 110万円 × 40%)- 125万円 = 231万円
※1保険金を含め受け取った金額の年間合計額
※2 贈与税の基礎控除分(暦年課税は年110万円)
贈与税 231万円
一時所得の場合
(保険金(1000万円) - 支払った保険料 -50万円)= 一時所得の金額
※一時所得は、その所得金額の2/1に相当する金額の1の金額を給与所得などのほかの所得の金額と合計して総所得金額を求めたあと、収める税額を計算します。
一時所得は所得税がかかるため、税額は保険金を受け取る人の所得によりますが、保険金から差し引ける部分もあり、贈与税より安い税金で済みます。
贈与税がかかる契約形態になっていると、税率が高く、控除額も少ないので、保険金が税金で大幅に減ってしまうことに。
加入中も契約者と受取人の変更はできるので、贈与税がかからないように変更したほうが、税額面ではおトクです。
生命保険相談はこちらをクリック
無料ガイドブック(PDF)プレゼント!
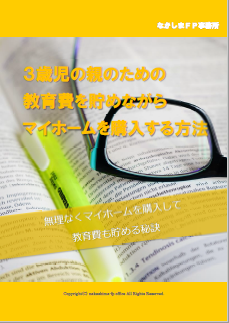
PDF版(15ページ)
3歳児の親のための教育費を貯めながらマイホームを購入する方法
このガイドブックを読むことで
・無理なく買えるマイホーム金額の算出方法とは?
・変動金利VS固定金利どちらがお得?
・劇的に教育費が貯まる3つの秘訣
など、マイホーム購入のポイント、効率的な教育資金の貯め方、貯蓄が増える家計の管理方法など、具体的な方法がわかります。
これまで600世帯以上の家計を見直した中で、これだけは知っておいてほしいというポイントをまとめました。
あなたのマイホーム、教育資金の準備にお役立てください。
ガイドブック無料ダウンロードはこちら
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
なかしまFP事務所トップページ
お問い合わせはこちら
無料小冊子プレゼント
事務所概要
なかしまFP事務所
代表者:中嶋 健三
プロフィールはこちら
ご相談場所
〒221-0835 神奈川県横浜市
神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル7F KFPオフィス
本社事務所
〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町291-13
ご連絡先はこちら
事務所概要はこちら
交通・アクセスはこちら